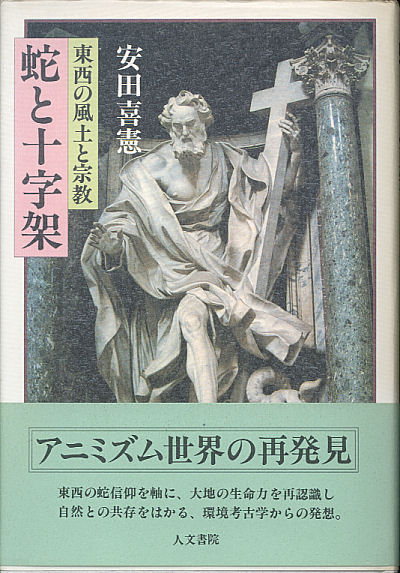
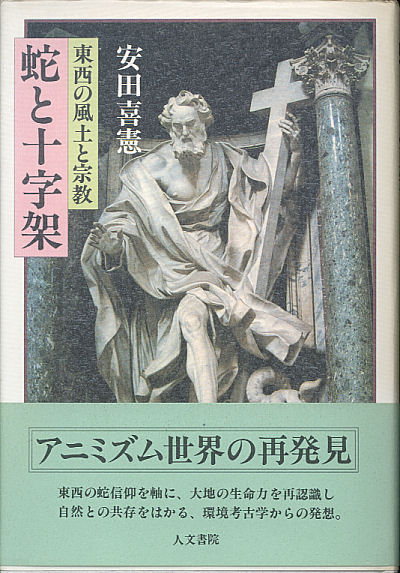
![]() �u�ւƏ\���ˁv
�u�ւƏ\���ˁv
�����̕��y�Ə@��
���c�쌛���@�l�����@

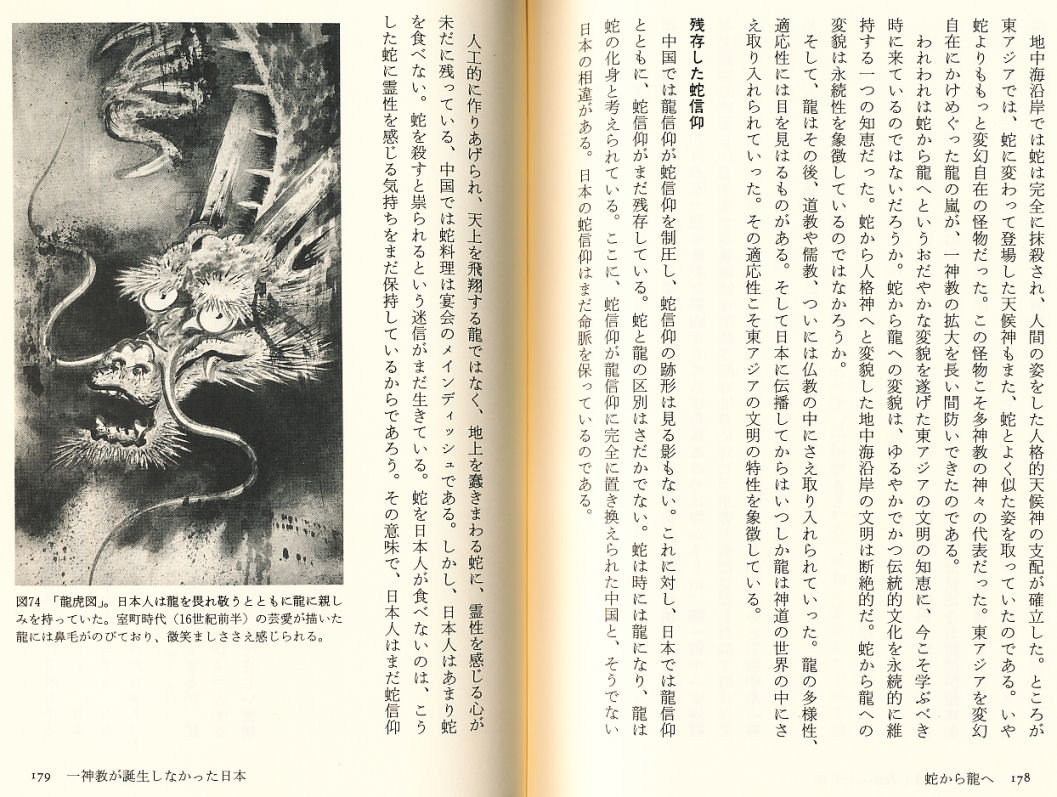
|
���قǖ��ڂɗ��ݍ����Ă���B���������̕��y�Ƃĕs�ς̂��̂ł͂Ȃ����Ƃ́A�ꕶ ����̂���ƌ�����{���r���Ă��e�Ղɑz�����邱�Ƃ��o���邩���m��Ȃ��B�E ��������������A�ꕔ�̕x�҂����肾�����Ƃ�����Ă����ꕶ����̐_�͐X�ɐ� ����ւ������B��n�̏��_�̃V���{���ł������ցA����̓C���f�B�A���E�z�s���̋V�� �ɂ������邪�A���펞��܂ł̌Ñ�n���C���E�ɂ����Ă��_���Ȃ��̂Ƃ��đ��� ���Ă����B���̑�n�̖L���̏��_�̃V���{���ɓ����̂��A�����̈�_�� �̃L���X�g���ł������B�O�ʈ�݂̂̌���^���s�����_����_���ƌĂׂ邩�ɂ��� �͎����g�^�₪�c�邪�A�����̃L���X�g���͑��_����A�j�~�Y���̐��E�ςƑΗ��� ��`�Ő��܂�Ă����B�����ăG�f���̉��̕���Ɍ�����A���錫�������̑��݂Ƃ� �Ă̎ւ��U������B�܂�l�Ԃ����ɂ��n���x�z�̖閾�����n�܂�A���R�ɑ��� �̈،h�������A���㕶���̂悤�Ȓn���K�͂̊��j�Ђ���������Ă����̂��� ���B�ܘ_���̑�n�̏��_�̃V���{�����E�����Ƃ͐l�Ԏ���̗~�]�������߂ɍD �s���������������������邩���m��Ȃ��B���K�ȕ֗��Ȑ����̂��߂ɁA�X�⑼�� ���A�����]���ɂȂ邱�Ƃɉ��̒�R�������Ȃ��Ȃ������l�Ԃ���剻���Ă������ƁB ���̔w�i�Ɉ�_���Ƃ��ẴL���X�g���̑��݂��{���ł͓W�J����邪�A�܂������g �̒��ł͉�������Ă��Ȃ����ł�����B�������{���͓��m�̏ے��Ƃ��Ă̎ւƐ��m �̏ے��Ƃ��Ă̏\���˂����グ����r�����_�ł���A���㕶���ɓꕶ���ォ�� �����c���Ă����A�j�~�Y���̕K�v���������i��������͍�ł���B 2000�N9��7���@�iK.K)
�u�C���f�B�A���̌����ł���A�j�~�Y���ƃV���[�}�j�Y���v �u�A�����J�E�C���f�B�A���ւ̎��̑z���v
|
![]()
|
�{�������p
��ʂɂ����āA�C���f�B�w�i�̕�����N�����j��Ƃ������h��ꂽ���j�̑��ʂ� �����Ă����̂ł���B�������̂��Ƃ��ԁA���ɒ����ԁA�C���f�B�w�i�̐l�X�� �����ɂ��đi���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B����قǂ܂łɋߑト�[���b�p�����͋��� �ł������B�����āA���{�l���܂��o�ϗ͂���ɂ������A�悤�₭�{���Ő��m�����ƑΓ� �Ɍ�荇�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ����̂ł���B�������A�A�j�~�Y���E���l�b�T���X�� �l�������A���[���b�p�̐l�X��A�����J�̐l�X�ɑ��}�ɗ��������Ƃ͂Ƃ��Ă��v�� ��Ȃ��B�ނ����苭��Ȕ����ƏՓ˂މ\����������B�������A���̖{���̕� ���ł̌�荇���ƑΘb�Ȃ����āA�ǂ����Đ^�̍��ۉ����\�Ȃ̂ł��낤���B������ �O�ɂ͐^�̑Θb���K�v�Ȃ̂ł���B���Ă̏������C�ɓ���悤�Ɏ��U�����Ƃ͂� �������B�����ȍ~�A���{�͂��̓���I�����Ă����B�����������U���̂͂������B �ނ���{���̕����ɂ����A�l�ނ̖������J������\���Ƒn����������̂ł� �Ȃ����낤���B�{������邱�Ƃ��u�i�V���i���Y���v���Ƃ����ᔻ�́A���Đl�̘����� �낤�B�{������邱�ƂȂ����āA�^�̋����̎���͐��܂�Ă��Ȃ��B���{�̌o�ϐ��� ���x����������`�A���邢�͕��Â���ւ̏�M�A�����͑����ɓ��{�l���`���I�� �����Ă����A�j�~�Y���̐��_�ɔ����Ă���Ƃ��낪�傫���B����Ƀt�@�W�[���_�Ȃǖ� ���̕������J���\�����Ђ߂��n�C�e�N�ƃA�j�~�Y���̐��_�����̂������A�n�C �e�N�E�A�j�~�Y�������̎���̖��J�������͑Җ]���Ă���B���R�Ɛl�Ԃ������\ �ȁA�����Ă����閯���Ƃ�����@���������\�Ȑ��E�̎����Ɍ����āA���{�l ���ꕶ����ȗ��ꖜ�N�ȏ�ɂ킽���Ď��������Ă����A�j�~�Y���̐��_�̉ʂ��� �����́A����܂��܂����������ɈႢ�Ȃ��B�u�A�j�~�Y���E���l�b�T���X�v�ɂ͋��c �����`���K�v�ł͂Ȃ��B�v�͈�l��l�̐S�����̖��Ȃ̂ł���B�i�{�������p�j
�ȗ��̐��E�ς�_�X�̑̌n�����S�ɔj��邱�ƂȂ��������ꂽ�B���̓ꕶ����̐��E�� �̒��ŏd�v�Ȃ��͕̂�����`�̗��O�ł���B�B��A�V�ɂ̂ݐ_��F�߂��_���́A�K���x�z ��O��Ƃ����@���ł���B�������A�ꕶ�l�́A���������K���x�z�̎Љ���\�z���邱�Ƃ��ɗ͔� ���Ă����B�ꕶ����́A�ꖜ�N�ȏ�̒����ɂ킽�葱�����Љ�ł��邪�A���̎Љ�͕x���� ���̐l�X�ɏW�����邱�Ƃ�����Ă����Љ�ł������B���X�؍����搶�i�u���{�j�a���v�W�p�� �P�X�X�P�N�j�́A�k�Đ��݂̃l�C�e�B�u�E�A�����J���Ⓦ��A�W�A�̏Ĕ�����̎Љ�ɂ́A�� ���x����C�ɍĔz������V�X�e�������݂��邱�Ƃ��w�E���A���{�̓ꕶ����̎Љ�ɂ����� �ɂ悭�����x�̍Ĕz���̃V�X�e�������݂��Ă����\���������Əq�ׂĂ���B�ꕔ�̎x�z�� �ɑS�Ă̕x���W�����A�s���������܂�A�x�z�҂͂���Ȃ�x���l�����邽�߂ɐ푈���N���� ���D���J��Ԃ��B����͐��A�W�A�̔���_�ƒn�т���o�������K���x�z�̎Љ�̓����ł��� ���B����ɑ��A�ꕶ����̎Љ�́A����Ƃ͍��{�I�ɈقȂ��Ă����B�ꕶ����̐l�X�́A �ꕔ�̐l�X�ɂ̂ݕx���W�����邱�Ƃ�������A�Љ�I�ْ����ɘa���邽�߂Ɏ�p�I�V��� �Ղ��ɍs���A���a�ň��肵��������`�̎Љ�炭�ێ������B�ꕶ����ɂ͐l���E ��������Ȃ������ƍ����^�搶�i�u��n�@���{�̗��j�i�P�j�v���w�قP�X�W�V�N�j�͎w�E���Ă���B ���a�ň��肵��������`�̎Љ�ł́A�l���E���K�v�͂Ȃ������̂ł���B�ꕶ����Ɉꖜ �N�ȏ�ɂ킽���Ēz����Ă�����������������`�̓`���́A�퐶����ɓ����Ă�����A�y�� �̓��{�l�̐��_���E�ɂ͍������c���Ă����Ǝv����B�ꕶ���ォ��퐶����ւ̈ڍs�� �ɁA�ɒ[�Ȗ����̓���ւ肪�Ȃ��������Ƃ��A���������`���I���E�ς̌p���ɂ͍K�������B ���{�l�ɂƂ��ẮA�x���ꕔ�̐l�X�ɏW�����邱�Ƃ���������̂Ɠ����悤�ɁA�B��_�̂� �𐒔q����K���x�z�̐��E�ς�����邱�Ƃɒ�R���������̂ł͂Ȃ��낤���B�B��_ �݂̂𐳂����Ǝ咣���A���̐_�X�̑��݂�r�˂���@���́A�K���x�z��O��Ƃ����B������ ������`�̎Љ�𗝑z�Ƃ��Ă������{�l�̋�������ׂȂ������ő�̗��R�ł��낤�B�퍑 ����ɃL���X�g�������{�ɓ`�d�������A���{�l�͐鋳�t�������炵���V�����Z�p��m���� �͋��������������A�鋳�t�����ӎ��̓��ɂ������Ă����K���x�z�̗��O�ɂ́A�������� �����B���̕�����_�������Ƃ��Ĕr�˂���K���x�z�̗��O�ɁA���{�l�͋������邱�Ƃ� �ł��Ȃ������̂ł���B���{�ŗB��_���n�E�F�̐M���a�����邱�Ƃ��Ȃ��A���`�d���� ����L�����y���Ȃ������w�i�ɂ́A�ꕶ����ȗ��A���{�l���ꖜ�N�ȏ�ɂ킽���Ĕ|���� ���������I�`�����j��邱�ƂȂ��p�����ꂽ�Ƃ����_�������Ƃ��d�v�ȗv���Ƃ��Ă����� ���̂ł͂Ȃ��낤���B�B��_���n�E�F�݂̂��ΓI�ɐ������咣����퓬�I�ȊK���x�z �̐��E�ɑ��A������`�ɗ��r�����ꕶ����ȗ��̓��{�l�̐��E�́A�܂��������Η����� ���̂ł������B�B���̐_�݂̂��������Ǝ咣�����_�����A���{�ɍL�܂�Ȃ������� �́A��_�����܂������K���x�z��O��Ƃ��Ă͂��߂đ����ł��邱�Ƃ���{�l�������I�Ɋ� ���Ƃ��Ă�������ł��낤�B�K���x�z�̎Љ�̊댯�����A�B���̐_�݂̂𐳂����Ǝ� ������鋳�t�̎p�̔w�i�ɓǂ݂Ƃ��Ă����̂ł���B �i�{�������p�j
���邱�Ƃ���������Ă����B���@�v�z������ł���B��������̉�X�͕�����L���X�g���A �C�X�������Ƃ���������@���ɂ͎����Ȃ����̂悤�ȍ��o�Ɋׂ��Ă���B����͌��㕶���� �i���ɂÂ��Ƃ������o�ƍ��͓����ł���B�l�̖��͌��肠����̂ł���A�l�ɂ͒N�������� �K��邱�Ƃ��������̑m�����A����̐M����@�����I��ɋ߂Â����邱�Ƃ͐����� ���B�l�̖��ɂ͌��肪����̂ɁA����t�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��������̌��� ���A���̐��E�ɂ��I�肪���邱�Ƃ͐����Ȃ��B����́A�����������҂́A����ȑg�D�̒��ŁA ���X�����ɕ�炷���Ƃ��ł���̂ł���B�����l�Ԃ̍K���݂̂��l���Ă�������@���́A �m���Ɏ����}������B���łɎ��̂ƂȂ�A�@���{���̖����������n�߂��@�h������� �ɁA���c�̐l�X�͂��̊�@�̎��o�����Ȃ��B���Ă����Ȃ鋐��ȕ������A�����Ȃ鋐�� �ȏ@�������B�i���s�ł̕����A�s���̏@���Ȃǂ͂��̐��ɂ͑��݂��Ȃ��B�����̎��� �Ƃ��ɂ��̕������x�����@�������ʁB�����Ă��̎��������炷���̂́A���̕����Ƃ��̏@�� ���x�������Ȃ̂ł���B�Ñ�n���C�����͐X�̕����������B�~�m�A�������M���V�������� �X�̕����������B�����̃V���{���ł���_�a�����̂ɂ��A���Օi�̓y����Ă��A���� �B����ɂ��X���K�v�������B�����Ă����A�o���邽�߂̑D���łł��Ă����B���� �����̔��W�͐X��j���B�X�̏��ł͎����̕s���������炵�������ł͂Ȃ��B�X������ ����n�͓~�J�ɐN�H����₹���Ƃ낦���B�N�H���ꂽ�y��͉����ɉ^��o�ς̒��� �@�\���ʂ������`�߂��B�����āA�`�߂����n�̓}�����A��̑��A�ƂȂ����B�Ñ� �n���C�������x�����X�̏��ł́A�o�ϋ@�\�����łȂ��A�l�X�̌��N�����ނ��B���� �ɂ��̐X�̏��ł͐l�X�̐��_���E�ɂ��傫�ȓ]���������炵���B�X�̏��ł͐_�X�̎��� �Ӗ������B�X�̐_�A�b�e�B�X���A�L���̏��_�A���e�~�X���Ǖ����ꎀ�B�Ñ�n���C�� ���_���̐_�X�ɂ�����ĐX�̂Ȃ������Œa�������L���X�g�����n���C���E��Ȋ������B ����̓A���v�X�Ȗk�ł������������B�A���v�X�Ȗk�̐[���X�̒��ɂ́A���Ȃ�I�[�N�� ���q����h���C�h�m�������B�������[�}����ȍ~�A���[���b�p�̐X���j��A�J��� �ƂƂ��ɁA�X�̏@���h���C�h���͒Ǖ�����E���ꂽ�B�h���C�h���̎��ƃ��[���b�p�̐X�̏��� �͋@����ɂ��Ă����B�������܂��X�̏@���ł���B�߉ނ��܂��X�̒��Ō����J���A�X�̒� �Ŏ��B�X�̒��Œa�����A�X�̏@���̐��i�����������������������c�邽�߂ɂ́A�X�� ��邱�Ƃ����Ȃ��̂ł���B�����̓N�w�̌��_�͐X�̒��ɂ���B�X��Y��A�X��j�� �s�ׂ́A�����ɂƂ��Ă͎��łւ̑����Ȃ̂ł���B���������̓��{�ŁA�ǂꂾ���̕��� ���c�����R�ی�ɐX�̕ی�ɐ[����������Ă��邾�낤���B�X����邱�Ƃ���������錴 �_�ł��邱�Ƃɖڊo�߂Ă�����{�̏@�h���ǂꂾ�����邾�낤���B�n���Ɛl�ގj�ɂ͎��� ��������Ƃ����̂��������̌��_�������B�����炭�����Ƃ����ǂ����̃J���}���玩�R�ł� �邱�Ƃ͂ł��܂��B�{���̖��@�̐��E���܂��Ȃ��K��悤�Ƃ��Ă���Ƃ����̂ɁB���@�̐��E �͂������A�����ɐV���ȏ@���̒a���ł�����B���ăo�����������畧����W���C�i���� �a�������悤�ɁA���{�ł͖��@�̎v�z�����q�����̒a���悤�ɁA����Ƃ������� �͊����̏@�������ɁA���̒�����V���ȏ@�����a�����鎞��ł�����B���ꂪ���̂��� �Q�T�O�O�N�ڂ̃J���}�Ȃ̂ł���B�Q�T�O�O�N�O�A���R�̍K���ł͂Ȃ��l�Ԃ̍K�������߂� �@�����a�������B���̏@���͐X��j�A�M��Ǖ����A���̒n����ɐl�Ԃ̉����� �������邱�Ƃɐ��������B�������ꂩ��Q�T�O�O�N��A�n���͐l�Ԃ̗~�]�ł��ӂꂩ����A �ɁX�����敾�����B�������͍��A������@���̏o���_�ł���A�j�~�Y���̑�����v�� �N�������Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B���������܂�������A���A���邢�͎R���ɂ��� ��܂ō�������B�����h���،h�̔O�Ɛe���݂������Ă������Ă����B�����Ɏ��R�� �Ƃ��ɋ�������v�z�̌��_������B�A�j�~�Y���̓��[���b�p�̃L���X�g�����E�ł͎肠�� �ɂ悲�ꂽ����ɖ��������t�ł���B��c�c���搶�i�u�A�j�~�Y������v�@���قP�X�X�R�N�j �͂���܂ł̃A�j�~�Y���Ƃ͋�ʂ���Ӗ��ŁA�����������R�Ƃ̋����̎v�z���l�I�E�A�j�~ �Y���Ƃ��ł���B�u�R�쑐�؎��F�����v�̋����⓹���̎��R�N�w�̎v�z�̌��_�ɂ��� ���̂́A�ꕶ����ȗ��̃A�j�~�Y���̓`���ł���A�߉ނ̎��R�~�ς̂��߂̎̂Đg�� �����ł��낤�B�����̐�B�́A���̎߉ނ̎��R�~�ς̋����̒��ɂ����A�^�ɐl�Ԃ��~�� ���铹�����邱�Ƃ�q���Ɋ�������Ă����B�����̒��ɃA�j�~�Y�������A���R�~�ς� ���߂̐g�̋Ƃ��s�����Ƃ������A�����̕����E�ɋ��߂��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
|
|
�͂����� �T�@�ւ��_���܂��������� �P�@�n���ւ̏�O �Q�@���ߓ�͎ւ����� �R�@�ւƏ\���˂����������� �S�@�n���C�͎M�̒��S�n �T�@���܂ꂩ��鑾�z�Ǝ� �U�@�ւ������E�̎x�z��
�U�@�ւ��E����_���̒a�� �P�@�ւ��E���_�X�̓o�� �Q�@���[�[�̏\���̕��y �R�@���̏ے��ɓ]�������� �S�@���R�ς���ς�������_��
�V�@���������̑�E�C�ւ̓� �P�@�����ɂȂ������f�D�[�T �Q�@�����ɂ��ꂽ�������� �R�@���������̗�͂̐���
�W�@�ւ��痴�� �P�@���̋N���Ɣ��W �Q�@�ւ��痴�ւ̕ϗe �R�@�_�b�̋��ʐ� �S�@��_�����a�����Ȃ��������{
�X�@�A�j�~�Y���E���l�b�T���X �P�@�����Փ˂̎��� �Q�@�V�����Ȋw�̑n�� �R�@������`�Љ�̎��� �S�@�X��A����@�� �T�@�A�j�~�Y���E���l�b�T���X
���Ƃ���
|
2012�N6��11���A�t�F�C�X�u�b�N�ihttp://www.facebook.com/aritearu�j�ɓ��e�����L���ł��B  �u����ȉ������ɗ������������̐�m�v�E�E�E����ɂĎB�e �M���V���_�b�̂Ȃ��ŁA�y���Z�E�X���A���h�����_�P��������Ƃ��ɗ��p�������h�D�[�T�́A�������̂�� �ς���ڂƓŎւ̔������|�낵�����݂Ƃ��Č���Ă��܂����B ����ɑ��ċ����[���v��������܂��B�u�X����镶���E�x�z���镶���v���c�쌛��������p���܂����A 5��7���ɓ��e�����u�ꕶ�̃r�[�i�X�v�Ɍ�����悤�ɁA�y��̑S�Ă��傫�Ȗڂ������Ă����킯�ł� �Ȃ��Ǝv���܂��B�������A���c���i���s��w�����j�̎��_�̓M���V���_�b�Ƃ͑S���قȂ����Ñ�̐��E�ρA ���̎��_�����̌���ɖ₢�����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����̓��h�D�[�T�̎ւɊւ��Ă��������� ��������̂��Ǝv���܂��B �������� ���̐X�̐����Ɠ����悤�ɁA�l�Ԃ̐������܂������Ă̂��A�Đ��������Ƃ����肢���A�ڂɑ���M�� ���݁A����Ȗڂ̓y������A���h�D�[�T�̓`���̂ł���B �������������ƌ��߂鋐��ȓy��̖ڂ�h�D�[�T�̖ڂɂ́A�X�̂����낪����Ă����̂ł���B ����́A�Ñ�̐l�X���X�Ɉ͂܂�Đ������Ă��ƂƐ[����������Ă���Ǝv���B �Ñ�̐l�X���[���X�Ɉ͂܂�Đ������Ă������A���������������ƌ��߂��n�̐_�X�̎������������B ���̐X����肩���邱����ɑ��āA�l�X�͈،h�̔O�����߂āA����Ȗڂ����������`�����̂ł���B ��n�̐_�X�̏Z���ł���X�B �������A���������l�Ԃ����߂�ڂ����������́A���鎞�������ɂ��č���Ȃ��Ȃ�A�������̉ʂĂɂ� �j���B ���h�D�[�T���_�a�̗�����S�����Ɨ��Ƃ���A�C�[�X�^�[���̃��A�C�������|����A�O���͂̐��̃}�X�N�� �j��A�R�₳�ꂽ���A�����ēꕶ�̓y����Ȃ��Ȃ������A����͐X���������j��������ނ�����A ���ł������ł��������B �X���Ȃ��Ȃ�X�̂����낪����ꂽ���A�l�X�͎������������߂鋐��Ȗڂ��������������Ȃ��Ȃ��� �̂ł���B ���́A���̎��Ɉ�̎��オ�I������C������B �X�̂�����̎���̏I���ł���B���{�ł́A�ꕶ�����ɂR�O�O�O�N�ȏ�ɂ킽���č�葱����ꂽ����� �ڂ����y�A�퐶����ɓ���ƓˑR����Ȃ��Ȃ�B ���̔w�i�ɂ́A�X�Ɠ��{�l�Ƃ̊W�̕ω����[����������Ă����ƍl�����邦�Ȃ��B �퐶����̊J���́A��K�͂ȐX�єj��̊J�n�̎���ł��������B ���c��W���̊g��̒��ŁA������ӂ̐X�͔j��Ă������B ���������X�̔j�i�W���钆�ŁA�ꕶ�l�������Ă����X�̂����낪����Ɏ����Ă������̂ł��낤�B �������� (K.K) |
|
2012�N3��12���A�t�F�C�X�u�b�N�ihttp://www.facebook.com/aritearu�j�ɓ��e�����L���ł��B |
|
2012�N3��22���A�t�F�C�X�u�b�N�ihttp://www.facebook.com/aritearu�j�ɓ��e�����L���ł��B |
